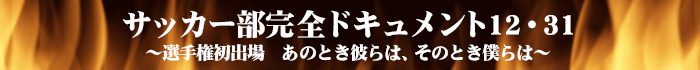
創部55年目にして、初の全国選手権を戦った
海星高校サッカー部。
監督と選手たちは、いかにして「その日」を迎えたのか。
同窓生たちは、いかにしてその戦いを見届けたのか。
それぞれの思いが交錯した12月31日、浦和駒場スタジアムまでの道のりを、監督への独占インタビューと同窓生の手記をもとに追った。
「僕の母校が、今年は出るんですよ」
海田修平は、知り合いの記者に得意げに話していた。絶対に応援に行こう。妻と、サッカーをしている長男、2歳になる次男を連れて、自宅のある東京から車を走らせた。
下村和也は、フットサル仲間5人を誘い、同じく会場に向かっていた。サッカー部員ではなかったが、いちサッカーファンとしては、まさに念願の初出場。県予選の映像は、事前にチェック済みである。
森勇仁がサッカー部の同期4人と乗り合わせて四日市を出たのは、試合前日、12月30日の夜9時。互いの近況報告や思い出話に花を咲かせつつ、海老名SAまでノンストップ。午前2時に埼玉に到着し、スーパー銭湯の酒臭い仮眠室で就寝。7時半に起床し朝風呂に浸かり、モーニングを食べてから会場へ向かった。
山下邦男は12月30日の早朝に四日市の自宅を出発していた。久しぶりの夫婦2人での旅行だった。築地市場へ行き、浅草寺で必勝祈願。夜は新橋の居酒屋で妻と晩飯を楽しんだ。31日は朝からスカイツリーに登り、朝日に必勝祈願。富士山がこんなに近くに見えるなんて、幸先がいい。
四日市発の一般応援バスで向かっていた福井茂人も、名古屋から新幹線に乗り込んだ小川真也も、快晴の空の下、車窓から見える富士山に、一様に心を奪われていた。あんなに綺麗に見える富士山は、初めてだった。
伊藤翔太は、現地での応援を希望した生徒たちの引率教員として、試合前日の夜11時に学校を出発したバスに乗っていた。日付が変わって3時間が経過しても車内の生徒たちはハイテンション。ようやく寝静まった頃に体調不良を訴える生徒が現れてその対応に追われ、一睡もできずにいた。
福元陽治が母校の決勝進出を知ったのは、ゴルフのプレー中のことであった。その翌日から、福元は自身がその情報を受け取ったときと同じ手段―SNSにより、喜びとともに各方面へ拡散した。選手権初出場に王手をかけた後輩たちの勇姿を、その目に焼き付けないわけにはいかない。津工業との決戦の日は、彼の彼女との、月に一度の約束の日でもあったが、交渉の結果、彼もまた決勝の切符をつかみとっていた。
「よーじ、良かったね。おめでとう」―試合終了後のスタンドで、たくさんの先生方から祝福の言葉をもらった。一番のファンでいてくれた両親からも、喜びの声を聞くことができた。7年間の月日を経て、念願をかなえた後輩たちの姿に、また、嬉しさが込み上げてきた。
全国大会の応援にも、もちろん行くつもりだ。いつも東京から会いに来てくれる彼女に「私には滅多に会いに来ないのに、母校の応援には来るのね」なんて言われようとも。
12月30日、Bチームは浦和学院高校にて練習試合を行っていた。埼玉の強豪校相手に2戦2勝という結果が、海星サッカー部の全体的なレベルの向上を物語る。彼らはAチームの応援に合わせて、全5日間の遠征を組んでおり、練習試合やトレーニングを行う予定である。貴重な経験をすべて自らの糧とし、来年こそは自分もと心に秘めつつ、明日は仲間のために精一杯の応援をする。皆が心に誓っていた。
「こっちや!もうすぐ始まるで!」
試合開始前の駒場スタジアムには、懐かしい顔があふれていた。小林一憲は、その中に同じクラスだった清水智大の姿を見つけた。清水は野球部OBだが、横浜在住で、かつての恩師に会いたくて駆けつけたとのこと。現在は母校の教員となっている小林には、そんな同級生の気持ちが何より嬉しく、清水もまた、旧友との思いがけない再会を一番に喜んでいた。サッカー部顧問・田中秀二とも固い握手を交わす。長く顧問を務め、ようやく手にした全国選手権の切符。その感慨の深さと強い意気込みが、ひしひしと伝わってきた。ウォーミングアップへ向かう2年生FW三輪翔真に拳を突き出しエールを送ると、それに気づいた三輪もまた、拳で応えていた。
上田周平は、得意先からの帰路を急いでいた。こんな時に限って、渋滞にはまる。家に着くと既にテレビがつけられていた。どうやらキックオフには間に合ったようだ。
会場にアンセムが流れた瞬間、森勇仁は母校の全国選手権出場をあらためて実感し、泣きそうになった。ワールドカップに初めて出たアフリカの小国の選手が、国歌斉唱の際に感極まって涙を浮かべるシーンを見たことがあるが、彼らの気持ちが今はとても良く分かると思った。
「普通に、やられますよ」
かつての教え子の言葉に、青柳隆は笑いながら返した。
「お前、ちゃんと解説せぇよ。海星褒めろよ」
この試合で、放送の解説を担当することになっていたのは、日本代表でも活躍した中西永輔氏。92年に行われた全国選手権で、四日市中央工業高校の選手とコーチとして共に戦った間柄だ。試合前に挨拶に来た中西氏とそんな雑談を交わしながら、しかし当時のことは「全然覚えてないな」と語る。「四中工のときは付いていっただけ。海星は母校やしな。それはやっぱり全然違うよ」
高校進学に際し、海星を選択した理由を「先生になりたかったから」と青柳は振り返る。
「本当は2月ぐらいまで四中工に行く気やった。でも、教師を目指すんなら海星のがええって担任に言われて」
教員志望であるなら工業高校より普通科高校の方が、ということであったのだろう。サッカー部があるかどうかも知らずに入学した海星では「入った瞬間からレギュラー(笑)」。当時の部員数は30人に満たない程度であったが、上級生には現在ヴィアティン三重で監督を務める海津英志などもおり、在籍時はインターハイ予選、全国選手権予選とも県3位の最高成績を残した。中学生時代に一緒にプレーしていた仲間が四中工で全国選手権に出ている姿を見て、悔しい思いもしたが、3年次には国体のメンバーに選ばれ、「秀二先生と一緒に山梨へ行ったことが一番の思い出」と語る。大学進学時は「教員を目指すなら皇學館へ」という周囲の勧めもあったが、サッカー部がないと分かり、中京大学へ。卒業後は、「北勢地区のどこかの中学校で講師でも」と考えていたところ、国体のときの縁で四中工の城雄士監督から声がかかり、サッカー部コーチに就任することとなる。そして3年後、海星サッカー部監督として母校へ凱旋するわけであるが、「海星で教えられたら、という漠然とした希望はあったけど、まさか実現するとは思っていなかった」と振り返る。
母校の監督として、初めて臨む全国選手権の舞台。青柳は全く新鮮な気持ちで迎えていた。正確に言うならば監督として、というより「いちOBとして」、「自分の後輩たちが出ている」という客観的な意識の方が強かった。開会式は、感動モノであった。本当は、スタンドから見てみたかったが、もっと言えばプラカードを持って一緒に行進したいくらいであったが、それができないのが少し惜しかった。
聖和学園が手強いチームであることは、百も承知だった。対戦を控え、試合映像の研究はもちろん、同じくドリブル主体のサッカーを標榜する野洲高校との強化試合も行っていた。前半は、まさにその対策が功を奏した。聖和学園の選手がボールを持った瞬間、複数でチェックし、高い位置で奪って一気にゴール前へ持ち込み、あとはシュートを決めるだけ―そんなシーンが、何度か繰り返された。18分にはMF桜井天海の縦パスからMF上陰統己が繋ぎ、抜け出したFW三輪がゴール正面でGKと一対一になりかけるも、シュートのタイミングが一瞬遅れ、相手DFにブロックされてしまう。その直後、三輪のCKをDF長谷川雄大が折り返したボールがバーに当たり、こぼれ球をMF中野泰良が狙うもわずかに枠を外れた。38分にはFW水谷恭平がゴール左からシュートを放つも相手GKの好セーブに遭うなど、先制点がいつ生まれてもおかしくはなかった。それに対し聖和学園は、愚直なまでに自分たちのサッカーを貫いていた。自陣深くからでもドリブルとショートパスで繋ごうとし、ロングボールや大きなサイドチェンジは皆無と言ってよかった。「これはいける」―現地で、あるいはテレビで見ていた多くの同窓生が、そう思っていた。青柳も、選手たちも、手応えを感じていた。「野洲の方が強いです」前半を終えて、選手たちからはそんな感想が漏れていたという。「何で前半0―0で終わってるんですか」試合後、個人的に親交のある聖和学園の加見成治監督からも、そう声をかけられた。敵将も失点を覚悟するほど、前半の主導権は海星が握っていた。ただ―
数多くのチャンスがありながら、1点を取ることができずにいた。初の大舞台に緊張していたのだろうか?青柳はきっぱりと否定する。
「全然、いつもと変わらん。朝から和気藹々とした雰囲気で、試合に入っても驚くほどのびのびとプレーできていた。ただ、あそこで決められへんのが海星やねん(笑)」
聞けば青柳自身も、現役時代から緊張はしないタイプ。観客が入っている試合ほど力がみなぎったという。『マインドハウスTC』時代には天皇杯でJリーグのクラブとも対戦したが「おおー!井原や!柱谷や!よし、真っ先に握手してやるぞってね(笑)」
そんな監督のキャラクターも、選手たちが大舞台に物怖じしない一因なのかもしれない。
しかしながらただ一人、FWの三輪翔真に関しては「あいつはガチガチやった」と振り返る。前回の県予選決勝で、途中出場ながら四中工相手に2得点して注目を集め、今予選でも決勝でのハットトリックなどチーム最多得点を記録していた2年生エースは、メディア取材などの機会も多く、重圧もあったのではと青柳は推し測る。「3年やったら、ちょっと言うとこやけど、2年生やしな。痛い目にも遭っといた方がええと思って、あえて何も言わんかった」ただ、そんな中でも、三輪の存在感は際立っていた。前線でタメをつくり、タイミングのいい動き出しでボールを引き出しながら、時には下がってゲームメイクにも参加しており、2トップを組む水谷恭平や、左サイドハーフの伊藤蓮らとともに、攻撃の中心を担っていた。
テレビでは、前半を終えての監督コメントが流れていた。「三重テレビが『監督!どうですか?』ってうるさいねん(笑)。見たらわかるやん、結構ええやんって」
組織的に守り、ボールを奪ったらシンプルにパスを繋ぎ、少ないタッチでフィニッシュまで持っていく。普段からやってきたことが、まずまずできていると感じていた。だからハーフタイムも、特に喝を入れるようなことはしなかった。「おーい、あと点決めるだけなんやけどぉー。頼むわ〜って」
そう言って笑った。当時の情景が、ありありと目に浮かぶ。おそらく本当に、このままのテンションであったのだろう。
その頃、北海道のとある牧場で、谷川翔大は馬房を作るため、藁を敷きながら、母校に想いを馳せていた。家庭の事情で転居したため、海星を卒業することは叶わなかったが、幼い頃からサッカーに親しんできた谷川にとって、サッカー部の全国大会出場は年の瀬の一大イベントとなった。出場を記念してつくられた携帯ストラップを購入し、当日に備えた。長年の浦和レッズファンとしては、駒場スタジアムからスタートして埼玉スタジアムを目指す戦いであるということも、感慨深いものであった。試合開始時は昼休みであったため、携帯を片手に同級生のSNSやインターネットにより、逐一試合経過を確認できた。現地の熱気が、雪深い北海道にも伝わってくる。昼休みが終わり、もう携帯を確認することはできなくなってしまったが、ストラップは眩いばかりに青く輝いていた。
海星が押し込む展開が続いた前半とはうって変わって、後半はオープンな打ち合いで幕を開けた。聖和学園が得意のドリブルを中心とした攻撃でペナルティエリアまで侵入しシュートに持ち込めば、GK中村勇之介の好セーブで難を逃れた海星はその直後、中盤で奪って三輪がドリブルで持ち上がり、左サイドを駆け上がってきた水谷へラストパス。ゴールを巻くように放たれたシュートは惜しくも枠を外れてしまったが、得点の匂いを感じさせた。
しかしながら、海星のプレスをかいくぐり、聖和学園がシュートチャンスを迎える場面が少しずつ増え始める。そんな中、聖和学園の「切り札」西堀選手の投入が、試合の流れを一変させる。
「聖和学園じゃないくらい早かった」
青柳がそう評するように、スピードに乗った細かいドリブルを武器にして、10番は海星ゴール前を混乱に陥れていく。「彼が入ってくる前に1、2点取っておきたかったんやけどな。(対峙するDFにも)お前のサイドで来るぞー!って言うてたんやけど」
その、対峙した背番号13番、星野皓輝には、密かに女性ファンが生まれていた。前半からメインスタンドに近い左サイドを疾走する姿に心を動かされ、声援をおくるフットサル仲間の女子を横目に、下村和也は後輩を羨んでいた。
後半20分を過ぎたあたりから目に見えてプレスが効かなくなりはじめていた海星は、MF中野に代えてMF木根原斎を送り出し、再び中盤の活性化を図る。スタミナに不安のあった中野と木根原の交代は当初から予定していたものだったが、このとき、木根原は足の痛みを隠していた。青柳は試合後になって本人から告げ知らされた。
「あれ? 様子がおかしいぞ? と思ってたら・・・。まあ、俺も(選手の立場だったら試合が終わるまで)絶対言わんけど。死んでも言わん」
目標はただひとつ。チームの勝利のために、各々が力を尽くして戦っていた。初めてインターハイに出場したときのキャプテン・伊藤祐輝は、「球際まで一人ひとりが気迫で追いかける姿に、昔からの雰囲気が受け継がれていると感じた」と後輩たちに温かいまなざしを向けていた。
ただ、ベンチから戦況を見つめていた青柳は、このあたりから嫌な予感がしていた。
「何度もチャンスがありながら、ウチが決めきれずに0-0で試合終盤まできている状況。そろそろやられるんちゃうか・・・」
後半35分、その予感が的中する。ペナルティエリア手前でボールを受けた聖和学園の藤井選手が左からやや中央寄りに進むと、右足を一閃。放たれたシュートは右に弧を描いてゴールへと吸い込まれていた。「あれ? 入った?」下村和也は友人たちと思わず目を見合わせていた。それまで再三、好守でチームを救ってきたGK中村が一歩も動けない、スーパーゴールであった。スタンドから見ていた山下邦男も、テレビ越しに観戦していた上田周平も、一瞬、何が起こったのか、理解できなかった。あと5分というところで先制された悔しさも相まって、「偶然に入ったのでは?」と思いたくなるようなものであったが、 「予選の映像も見たけど、彼はもともと巧い選手。あれは狙って入った。ディフェンスのチェックが2回、遅れたのが原因」と、青柳は冷静に振り返る。その2分後には、海星の左サイドを突破され、中央に折り返されると、走りこんできた西堀選手に決定的な追加点を決められてしまう。
すると、ここで海星は、FW武永健佑をピッチに送り出す。
チーム事情により、ベンチを温める機会も多かったが、腐らず共に戦ってきた3年生だ。
「足速いし、ひょっとしたら決めてくれるかな、という期待もあって」
最後まで諦めることなく1点を取りに前がかりになったことで、その後も立て続けにピンチが訪れた。しかしながら至近距離からの強烈なシュートはDF星野が体を投げ出して防ぎ、GKまでかわされた絶体絶命の場面ではDF深川瑠夏が懸命に戻って事なきを得た。
「きついところで踏ん張れるようになった。メンタル面での成長が大きかった」
選手権の切符を初めて手にすることとなったチームの要因を、青柳はこのように分析する。微妙な変化を感じ始めたのは県予選前の10月中旬、関西遠征のあたりからだった。選手権の常連校との数試合で、それまで精神的に「ゆるい」と感じていた選手たちが(それは同時に「緊張しない」という長所でもあるのだが)、相手の攻撃に対して「はね返す」力をつけていることに気付いた。もともと点は取れるチーム。ディフェンスが安定すれば、県予選も結構いいところまでいけるのではないか、という、かすかな期待が生まれた。実際、その後の県予選では準決勝までたったの1失点。津工業との決勝を合わせても3失点という結果で、念願の全国選手権出場を決めることができた。
しかし「ドベから3番目」と青柳は言う。もともとのチーム力は、ここ10年で下から3番目だそう。「一番弱かったのは沖縄のインターハイ行ったときのチーム。一昨年、県予選準優勝のチームが2番目」
そんな「ワースト3」のチームが、いずれも最終的に結果を出しているのは興味深い。
「こっちもリラックスするでかなぁ。まあ、選手たちには『史上最低』くらいに言うてるけどね(笑)」それはしかし、裏を返せば期待の表れ。選手たちのメンタルコントロールも、監督の手腕が発揮されるところである。
もうひとつ、今回のチームを語るうえで興味深いエピソードがある。青柳は指導者として、「選手にはサッカーだけでなく学校の勉強もしっかりやるように」という方針をとっている。海星サッカー部は今や百四十人を超える大所帯となったが、Aチームは“赤点”がゼロ。下のチームに行けば行くほど、赤点が増えるのだという。
「得意不得意はあると思うけど、どれだけ努力しているかっていうのは自然と表れてくる。提出物をしっかり出すとかね。そういうところで、卒業後も全然違ってくるから」
26歳で海星サッカー部の監督に就任して22年。就任当初は紅白戦もできないほどの部員数だった。四中工のCチームと対戦しても、全く歯が立たなかった。海星へ行くことが決まったとき、尊敬する城監督から「まず、10年頑張れ」と言葉をかけられた。有望な選手を獲得すべく、無理を言って三泗トレセンのスタッフに入れてもらい、精力的に中学校をまわった。最初は「海星なんか」ととりあってもらえなかった。しかし、地道な活動が実を結び、部員数も徐々に増え、奇しくも10年目に新人戦で優勝することができた。今でも、中学校への視察は毎日のように行っている。「海星なんか」と言われたあの頃から、「海星だったら」という反応に今は変わっている。監督同士の懇親会などにも顔を出し、人脈づくりにも余念がない。そうして得られたコネクションが、強豪校との練習試合を実現させ、チーム強化の一因となっている。
一方で青柳は、県をまたぐ、いわゆる越境入学による強化には否定的だ。現在、チームにはMF中野泰良とDF山田晋平という、2人の県外(愛知県津島市)出身者がいるが、彼らが在籍していた愛知FCの監督が海星の卒業生だったという縁があったことと、自宅から通える距離だったことから受け入れている。「新チームでも副キャプテンやし、彼らの存在は大きいけどね」
県外からの入部の問い合わせも少なくないが、「基本的にすべて断ってる。地元のチームでやってくださいって」
県内で長らく高い壁でありつづけた四中工に対しても、今の選手たちは特別な意識を持つことなく臨むことができているという。「俺らのときは死んでも当たりたくなかったけどね(笑)」実際、先頃のインターハイ予選でも3-0で勝利している。三重県内の勢力図は、急速に変わり始めていると言えるだろう。
試合後のロッカールームでは、やはり泣いている選手もいた。しかしその表情は、悔しさもありながら、「やりきった」という印象の方が強かったと青柳は記憶している。その晩、晴れやかな表情の選手たちにゲームセンターの前で遭遇した。
「先生、ゲーセン入れてくれないんですよぉ〜」
「当たり前や、あほぉ(笑)」
まあ、大人しい、いまどきの子たちらしいけどね。そう言って目を細める姿は、「良き兄貴分」そのものであった。
下村和也は、ともに観戦したフットサル仲間たちと「反省会」を開いていた。下村が自ら言い出したのではない。この日の試合に感動した友人たちによる計らいであった。試合終了のホイッスルが鳴ったとき、そのうちの一人は涙を流していた。「OBでもないのに・・・」何だか少し、申し訳ないような気持ちになった。同時に、こんな友人たちに恵まれたことが嬉しく、心の中で感謝していた。二〇一六年が、終わろうとしていた。
1月1日、Bチームは千葉に移動し、那覇西高校とのトレーニングマッチを行っていた。昨日、宿舎でコーチの高木徹からかけられた「ここにいる選手が、来年、あのピッチに立つことを目標にやってほしい」という言葉を胸に、新チームに向け切磋琢磨すること、そのために責任感を持ってプレーすることを、一人ひとりがあらためて自覚した。
1月2日は、ジェフ千葉のホームスタジアムであるフクダ電子アリーナに隣接する人工芝のピッチでトレーニングを行った。昼からは選手権の二回戦を観戦し、同世代の高いレベルのプレーに、大いに刺激を受けた。その中にはJリーグのクラブに入団が内定している選手もおり、観戦した3年生のひとりは「自分たちにもまだまだチャンスはある。今日からもっとトレーニングに励みたい」とモチベーションを高めていた。
全日程を終え、学校に到着したのは1月3日の夜8時。Bチームに帯同したサッカー部コーチ・上野健太は、マイクロバスの掃除をしている選手たちの姿に、遠征の成果を実感していた。そこには、「年末年始という時期に5日間の遠征ができたのは、周囲の多くの人のサポートがあったからこそである」という感謝の気持ちが、はっきりと表れていた。来年は三重県では追われる立場になる。このチームの中から、また全国の舞台へ、そして選手権初勝利へと導く選手が現れることを、上野は願っていた。
「海星サッカー部で学んだ挑戦することの大切さ、“攻めの姿勢”は今の自分のモットー。これからも攻めの姿勢を大切に悔いのない高校サッカー生活を送ってほしい」森勇仁は、前夜からの興奮冷めやらぬまま、後輩たちにエールを送る。もっともっと勝ち続けて、さらなる高みを目指してほしい。そしてまた、応援に駆け付けたい。弾丸ツアーは、いつまで続けられるかわからないけれど。
伊藤翔太は、学校応援バスでの生徒引率を終え、自宅へ向かっていた。復路の応援バスは、必死の応援の甲斐あって生徒も教員も熟睡、心穏やかに過ごすことができた。後から聞いた話では、別の車内は「紅白が観たい」だの「年越しに間に合うのか」だの、賑やかなことこの上なかったそうだ。帰宅し、時計を見る。あと20分で年が明ける。年越しそばをすすりながら、ようやく1年の業務が終了したことに、充足感を覚えていた。
「あのパスがすごかった。あいつが巧かった」
海田修平は、小学校2年生の長男からそんな感想が聞けたことに、少し驚いていた。これまで、日本代表の試合を観に連れて行ったこともあったが、「疲れた」「眠かった」などと言うばかりだった。その長男が、海星の試合は面白かったと言っていた。選手たちに近い距離で観られたぶん、同じくサッカーをしている身として心情的に共鳴するものがあったのかもしれない。また、連れてきてあげたいと思った。そのためにも、来年もまた、海星がこの舞台に出られるようにと、心から願っていた。そのとき、この子はどんな言葉で「お父さんの学校」の試合を語るようになっているのだろう。そんな楽しみも、胸に抱きながら。




